茨城には、あまり知られていない狐の四兄弟の民話がある。
兄たちは川を、野を、山を。
末の弟は海を守り、人々に恵みをもたらしたという。
そんな伝承を辿りながら巡るツアーを企画したところ、地元メディアにも取り上げられ、多くの方に参加していただいた。
これはその旅の記録であり、地域に残る“祈りの地”の案内でもある。
狐たちが誓いを立てた場所 ― 静神社(瓜連)
むかしむかし、静の森に四匹の兄弟キツネが住んでいました。誰が名前をつけたかはわかりませんが、いつしかキツネの長男を源太郎。次男は甚二郎。三男は紋三郎。四男を四郎介といいました。ある日、兄弟は話し合いをしました。「わたしたちの仲間には、人間や動物たちに悪さをする者がいる。とても残念なことだが、仲間の悪さを完全に止めることは難しい。だから、せめてわたしたちの持っている神通力を人間のために役立てよう。仲間の罪滅ぼしをするんだ。」こうしてキツネたちは人助けを誓います。まず、長男の源太郎が切り出しました。わたしは長男だから、本家のあるこの里を守る。里には大きくて重要な川が2つあるから、里と川の守りは自分に任せてくれ。お前たちは里を離れて開拓地の人間に協力するように」それに甚二郎が応えます。「それでは、わたしは野を守りましょう!」紋三郎も応えます。「それでは、わたしは山を守ります」最後に四郎介が「わたしは一番若くて元気もあるから、海を守ります!」相談を終えると、四匹は一斉に各地に分かれました。四匹が昼夜を問わずに川、野、山、海をかけめぐったお陰で、人々の暮らしは少しずつ良くなっていきました。源太郎のいる川では、魚貝類がたくさん見つかるようになり、人々はいつしかセリの栽培などもできるようになりました。甚二郎のいる野では、いつのまにか田畑の開墾がされていて、稲作が盛んになりました。紋三郎のいる山では、家をたてるために必要な土台石が次々に見つかるようになりました。四郎介のいる海では、大きな魚の居場所がわかったり、塩の作り方をひらめく人々が現れました。兄弟の活躍はそれで終わらず、新しい衣類やお酒の作り方、薬草の発見などにも関わりました。やがて、この地に住む人々は増えて各地に大きな館やお城が建ちました。そして、キツネたちはそれぞれの場所で守り神としてまつられるようになったのです。源太郎は瓜連城。甚二郎は米崎城。紋三郎は笠間城。四郎介は湊城です。
「四匹の狐の物語」楠見松尾 著「茨城のむかしばなし」より一部引用
四兄弟は「人のために力を使おう」と誓い合い、それぞれが担当する土地へ飛び立ったと伝わっている。
その舞台とされる山に祀られているのが、常陸国二宮・静神社。
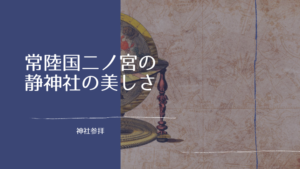
ある文献によると、舞台となった場所は「青山」となっているが、地図を探し見てもそれらしき表記がない。
よって、地理学的にこのあたりであろうといわれている。

瓜連(うりづら)という地名は、「瓜(うり)」に“けものへん”を付けると狐。
この土地が、彼らの故郷だった証なのかもしれない。
【長男】源太郎稲荷 ― 川と町を守る狐
私は山を、と言った長男の源太郎稲荷は、瓜連にある常福寺の外れに存在する。
静神社から車で10分ほどのところにある常福寺は、かつて瓜連城という城があった。
瓜連城の堀のほとりで、小さなお社がひっそり息づいている。

この地は、過去に幾度も戦火に晒された。
かつて南北戦争が起こった時、ここは楠正成の一族が居城していたが、対立する佐竹に攻め込まれ、落城してしまった。
その後、佐竹氏や水戸家の庇護を受け、現在は関東十八檀林の1つに数えられるほどの浄土宗の名刹となった。
その本堂の北側、堀の上にあるのがこの源太郎稲荷だ。
両脇のお狐さまは、静かだが、力強いまなざし。
笠間稲荷の鬼門を守る狐と似た表情をしているのが印象的だ。
北を見張るもの同士の、共有された役目なのか。
住所:〒319-2102 茨城県那珂市瓜連1222 常福寺内
【次男】甚二郎稲荷 ― 野と命を育む狐
田畑を一望できる坂の上に、素朴で清らかな小さな祠が建つ。

ここには「欲のない甚二郎」という話が残る。
人々が実りに恵まれるように、静かに働き続けた狐だったのだろう。
ただし米崎城の存在は文献で不明瞭。
一時は三嶋神社に身を寄せていたという話もあり、場所やルーツが今ひとつ分からない。
その曖昧さもまた、伝承が生き続けている証のように思える。
【三男】紋三郎稲荷 ― 山と知恵を授ける狐
笠間稲荷は日本三大稲荷にも数えられる大社。
石や陶芸の盛んな笠間の地で、紋三郎は“山の恵み”をもたらした狐と伝わる。

笠間稲荷は、別名胡桃下稲荷ともよばれている。
この胡桃下という名前のいわれについてはこんな民話が残されている。
笠間稲荷神社にまつわる言い伝えをもう一つ。むかし、奥州の棚倉藩主にたいそう鷹狩りの好きな殿様がおり、たくさんの鷹を飼っておりました。ところが、ある日、殿様がかわいがっていた一羽の姿が見えなくなってしまったのです。家来たちが必死でさがしまわりましたが、見つけることができませんでした。そこで、「これは狐の仕業に違いない。明日にも、このあたりの狐を残らず退治してしまおう。」ということになりました。その晩のこと、殿様の夢の中に老人があらわれ、「私は、笠間の紋三郎と申す者である。私に考えがあるので、狐狩りを三日ほど待っていただきたい。」というのです。殿様は老人の願いを聞き入れ、狐狩りを延期することにしました。そして、三日後の朝のこと、さがしていた鷹が玄関先の敷石の上に戻っており、その傍らに一匹の老いた狐が横たわっていたのです。「あの老人が悪さをした狐を捕らえ、鷹を連れ戻してくれたのか・・・・」 たいそう驚いた殿様はさっそく使いを出し、笠間の紋三郎という老人をさがさせました。ところが、紋三郎という人物は実在せず、それは笠間稲荷神社の俗称であるということがわかったのです。殿様は、「誤って罪のない多くの狐の命を奪うところであった。」と神様に感謝し、「大のぼり一対」を笠間稲荷神社に奉納し、後々まで信仰したということです。
参考図書「笠間の民話」(笠間市生涯学習推進本部) 「笠間市の昔ばなし」(笠間市文化財愛護協会編) 「茨城の伝説」(今瀬文也・武田静澄共著)
先に紹介した、胡桃下稲荷の語源となった「胡桃を落としていった老人」というのが、この紋三郎稲荷と同一人物であるらしいとのこと。
狐は神通力を持っており、夢枕にたったり不思議な力を与えたり、人々に知恵を授けたりして力を強めていくと上位の階級に成長することができる。
しかし、野狐と呼ばれる狐のグループは人に悪さをしたり不幸にしたりする。
紋三郎は、そんな狐をこらしめて罪なき狐たちを救ったのだろうか。
住所:〒309-1611 茨城県笠間市笠間1番地
【末弟】四郎介稲荷 ― 海を静める若狐
最後に、一番若く「海を守る」と宣言した四郎介が祀られている神社が那珂湊にある。

海辺の稲荷として、漁師の命を守ってきた四郎介。
代々“宮司名を継ぐ”ほどに尊崇されている。
四郎介は湊城を守ったと言われているが、この那珂湊にそういったお城があったという記述は見当たらない。
徳川光圀公の命により1698年に建設された水戸藩別邸、い賓閣がこの稲荷神社の近くにあるが、どうやらこの別邸のことを地元の住民が「湊城」と呼んでいたらしい。
かつては参道が人で溢れ、船の灯りが境内を照らしたと聞く。
震災があって海は静かになったが、今も昔も変わらず町の人々を見守り続けている。
住所:〒311-1229 茨城県ひたちなか市湊中央2丁目2−25
茨城を守る稲荷神社四社
稲荷神社の御祭神はほとんどが宇迦之御魂。
五穀豊穣の神であり、主に稲にまつわる神様だ。
偶然か、ホツマツタエにこのような記述があった。
先程からその一部始終を見ていたアマテル神から、ここで詔のりがありました。
「カダの神の温情に免じてミツヒコ(三彦)と配下のキツネ共の事、今回は特別に許そう。そのかわりキツネ共に全員ウケノミタマ(宇迦御魂神)を末長く守らせよ。もしも約束をたがえる事あらば、直ちに死刑にせよ。」
「カダの神!なんじにこの者共を今日より部下としてつけるにより、良き民となすべく指導せよ。」
カダの神は、アマテル神からキツネ共の恩赦を受けると、その課せられた条件をミツギツネに告げました。
「兄彦はここ宮中に残って御食(みけ)を守れよ。中彦は山城の花山野に行き、又弟彦は東国のアスカ野に下り、それぞれ三方に分かれて田畑の鳥やねずみを追う仕事をせよ。まめなせ。」今回の天照神の詔のりにより、キツネ共はウケノミタマとウケモチと、カダの三神(稲生・稲荷神)の守護役として後世までも付き従い、民の御食をお守りすることとなりました。
株式会社 日本翻訳センター
衣食住に不自由しないように、生活が豊かになるようにと言う人々の願いとともにあった稲荷神社。
四兄弟が守った、川・野・山・海。
そのまま、茨城という土地が持つ四つの表情だ。
狐たちはただの霊獣ではなく、暮らしの循環を守る象徴だったのかもしれない。
茨城を守った四匹の狐の兄弟。
その物語は、今も道の先で息づいている。
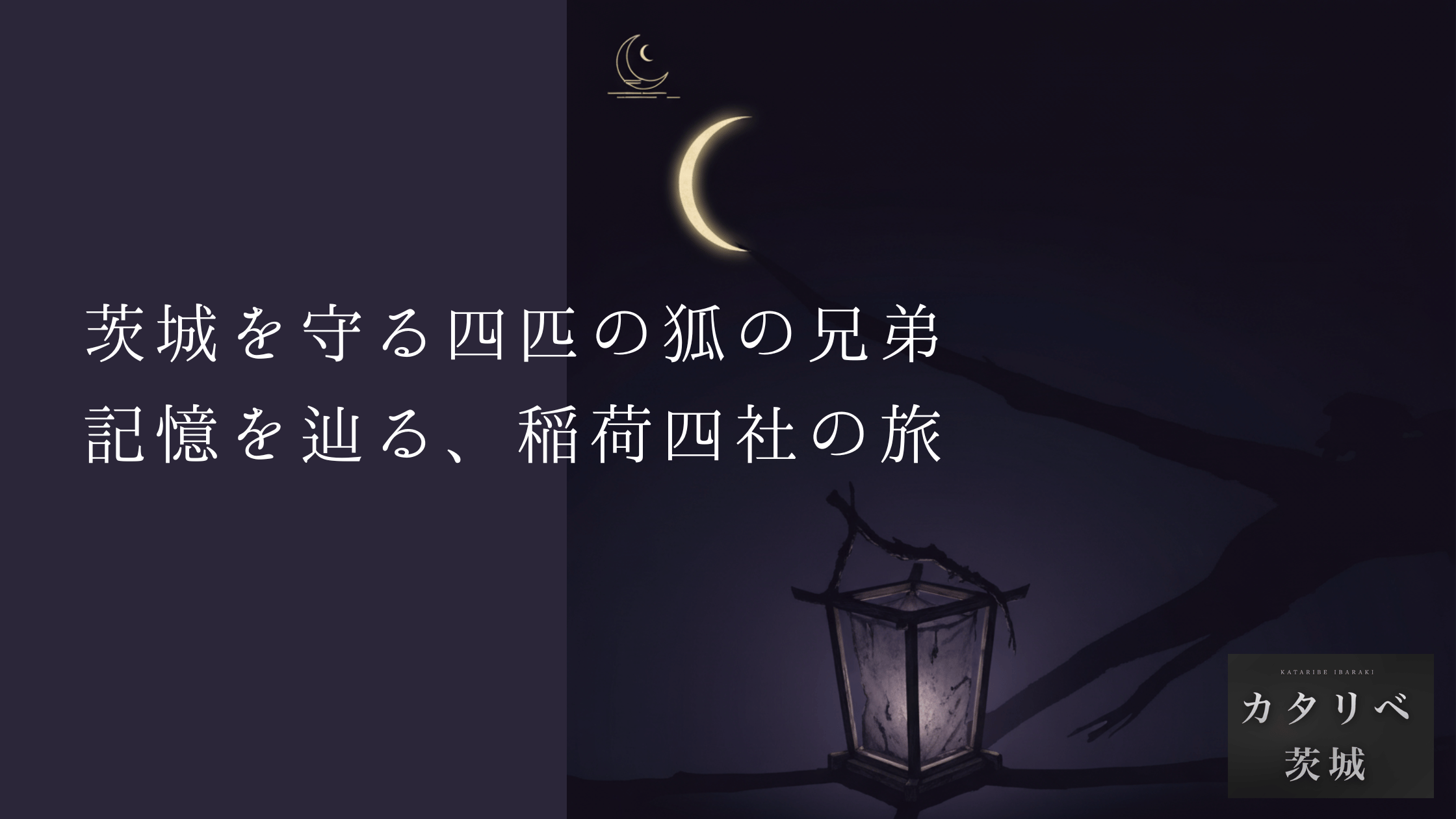
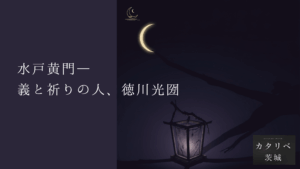
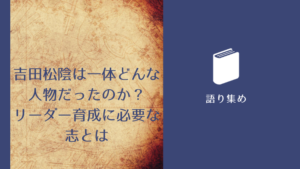
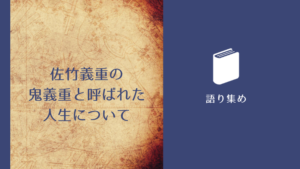

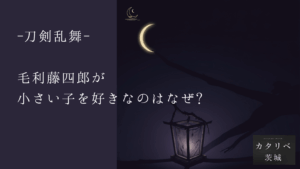
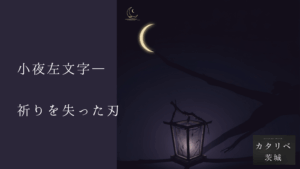


コメント