戦前、終身という科目があり今で言う小学校(当時の尋常小学校や国民学校)では必ず学ぶ人物がいました。
それが上杉鷹山。
先日、たまたま手にとった本が素晴らしく、子育て世代や自営業、あるいは経営者として人の上に立ち指導する方には一度読んでいただきたいと思うので一つブログに残しておくことにします。
十七歳の藩主、上杉鷹山誕生
上杉鷹山の名前を聞いたことがあるかたはどのくらいいるでしょうか。
私は東北の出身ですが、かれこれ30年近く耳にしたことがありませんでした。
九代目米沢藩主 上杉鷹山公
[伝統の社]米沢市上杉博物館
「成せばなる 成さねばならぬ 何事も」 改革者の功績を振り返る
蚕(かいこ)のまゆ
上杉鷹山は、宝暦元年(1751年)7月20日、日向国(ひゅうがのくに~宮崎県)高鍋藩主「秋月種美(たねみつ)」の次男として、江戸で生まれました(幼名「直松」)。母の「春姫」は、四代目米沢藩主「上杉綱憲(つなのり)」の孫娘でした。 宝暦10年(1760年)に八代目米沢藩主「上杉重定(しげさだ)」の養子となり、元服(成年の儀式)の際に名を「治憲(はるのり)」とします。翌年の明和4年(1767年)に、家督を継いで弱冠17歳で九代目米沢藩主となった治憲(鷹山)は、傾いた米沢藩を救うため、まず「大検約令」発し、役人の贅沢や無駄を正すことから、藩政改革への第一歩を踏み出します。 その後、農政を改革し、教育を進め、産業を発展させていくのですが、最も大きな産業開発は「織物業」で、置賜特産の青芋(あおそ)を原料とした縮織(ちぢみおり) に始まり、これらを基として養蚕(ようさん)・絹織物へと発展していきます。 鷹山という名前にしたのは、52歳からで、文化3年(1806年)には、56歳となった鷹山が「養蚕手引」を発行・配布します。文政5年(1822年)に72歳で死去しますが、生涯を米沢藩の人々のために尽した功績は、初代 上杉謙信と並んで後世に語り継がれています。
鷹山が藩主となったのは、17歳のとき。
若くして後を継ぐことは珍しくなく、その場合は後見人が実質実権を握り事実上の政治を行っていましたが、鷹山の場合はそういった人がいませんでした。
上杉家の藩祖は上杉謙信。
それが、後継者を指名する前に亡くなったため、養子であった景虎と景勝の間で相続争いがあり、最終的には景勝が跡継ぎとなりました。
景勝の頃、豊臣秀吉の配下になり会津に移され、百二十万石に。
その後徳川家康により厳罰の意味で三十万石に減らされ、領地は米沢に移されました。

それから三代目四代目と続いたのですが、四代目綱勝の正室媛姫が興し入れの二日後に死亡。
悲しみに暮れる綱勝もまた、二七歳という若さで逝去。
このままでは御家断絶となったところを、媛姫の父である保科正之が責任を感じ、綱勝の妹である富子が吉良上野介義央に嫁ぎ長子山之助を設けていたことから、彼を後継人とし、上杉綱憲を十五万石で取り立てるという名目で存続になりました。
五代目藩主の綱憲が誕生したものの、その財政負担はかなりのもの。
吉良家への援助も増え、藩の財政は火の車。

そのため、家臣からの臨時の課金の徴収や、農民に対しての増税などで取り立てる一方で裕福な商人からの借金が年々増加とあって、八代目重定の頃には領民も減っていたそうです。
状況を打破する力
重定には実子がいたのですが、綱憲の娘豊姫の孫である治憲に後事を託そうとしました。
治憲は早くに母をなくし、祖母のもとで育てられていました。
その賢さはお墨付きだったようで、豊姫は重定の娘である幸姫の婿養子として勧めました。
そして、1767年に家督を継ぎ九代目となりました。

まず鷹山が行ったのは、江戸の家臣に対しての大倹令です。
今までは単なる税の取り立て、課金の徴収などが行われるだけでしたが、鷹山はまず生活を見直し贅沢を禁じるということを大体的に打ち出しました。
その中には、神事や仏事の行事を取りやめたり延期したり、あるいは祝宴や贈答の禁止、一汁一菜や木綿着用などを命じたり、養父重定の妻が尾張家から連れてきた女中を一挙に減らしたり、とにかく出費を抑えるようにと広めました。
また、家臣たちだけでなく自身の仕切り料についても大幅にカットし、藩主となる前の二百九両のまま据え置き、それは隠居となるまでの五十年余続いたと言われています。

いきなり入ってきた若い藩主に生活を切り詰めよと言われても、反発が起こるのは想定済み。
鷹山は、江戸の家臣に対して命じたの文章をさらに懇切丁寧に書き直し、執政千坂高敦に命じて国元である米沢に届けさせました。
想定通り、やはり反発の手紙があり、鷹山は国の安危に関わることであるとして謝罪と懇願の気持ちをしたため二回目の手紙を送りました。
それでもなお、反発を繰り返す老臣達の噂を耳にした養父重定は直々に家臣を米沢城に集め、あらためて大倹令を発布。
家臣たちも先代藩主にそこまでされてはという遠慮もあり、とうとう従うことになったのです。
一度ならず二度も襲った災難
鷹山が国元米沢で体験したのは先勤争いでした。
明和6年(1769)10月に初入部、翌年1月開催の鉄砲上覧で、三手組の御馬廻
米沢の歴史を見える化
(謙信旗本の由緒)と五十騎(景勝旗本の由緒)が先勤(最初に打つ)争い
御馬廻と五十騎、交互に先勤を行てきた。順番的には五十騎が先勤の年であ
ったが、三手筆頭(分限帳など格式上ではトップ)の御馬廻が、初入部の際は
特別で、格上の御馬廻が先勤と主張、紛争となった(寛永4年・享保11年にも
紛争)。
鷹山、両組及び与板組の首脳を呼び、諸々と諭す。説得を受け、五十騎先番
と、の回答を出すが、配下の不満で紛糾、御馬廻トップが罷免の状況に至り混
乱状況となり、奉行等の藩首脳は鉄砲上覧の中止を検討、鷹山が再度両組首脳
に懇願した。御馬廻から後番を勤める、五十騎からは鷹山指示に無条件で従う
旨を受け、鷹山は後番を申し出た御馬廻にお礼の言葉をかけ、順番通り五十騎
を先勤として開催した。
ここにあるように、先代の上杉謙信と景勝それぞれへの思いがあり、これについては老臣たちも長年頭を悩ませて、様々な手段をもって妥協を試みましたがことごとく衝突。
どちらも譲らずという状況が百年余続いていたところを、鷹山は目先だけの解決だけではなく根本的からの和解をしなくてはいけないと、一度は執政が廃止という申し出をしましたが鷹山はこれを受け入れませんでした。
改めて両組の代表を呼び集めて話をし、誠意を持ってこれを伝え、次第に悟り始めた双方の態度が変化し、五十騎組から「格式が上である馬廻組に先勤を譲りたい」と声が上がり「いや、五十騎組に先勤してもらいたい」といいお互い譲り合ったという話が残っているそうです。
鷹山は喜び、双方納得の上で五十騎組先勤と決定し、無事に鉄砲上覧は滞りなく行われて百年余りの争いは幕を閉じました。
守りから攻めへ
災難を乗り越えた鷹山は、まず藩内の生産性をあげて収益を確保しようと試みました。
当時の農村は荒廃していて、生産性がかなり落ちている。ということは家計でいうと収入がガクッと落ちてしまっている上に、年貢の取り立てもあり田畑を捨てて逃亡する欠落が後を絶ちませんでした。
そして耕作人がいなくなってしまった田地は、捨て売りか無料で誰かに引き取ってもらうことになってしましたが、それでも引き取り手がおらない場合は手余地になったり村地になったりします。
それもまた、負債の一つとなり結局農村は荒廃の一途を辿っていたのでした。

そこで鷹山が起こしたのは、意識改革。
農民の意識を変えるために、「籍田の礼」という行事を作り自ら鍬を振るいました。
行事は無意味かもしれない、ただのおまじないに近いかもしれないけれど理屈を超えた感動があり、それは農民たちに感動を与え、農業に精を出すようになりました。
「籍田」とは古代中国の周の国で行われた儀礼で、天子(君主)が国内の農事を励ますため、自ら田を踏み耕し、収穫した米を祖先に備えたことから始まったものです。
籍田の遺跡
この故事を学んでいた鷹山は、凶作などで困窮し、働く意欲を失ないかけていた米沢藩の農民を奮起させようと、安永元年(1772)自ら籍田の礼を行うことを決心しました。鷹山22歳、明和6年の初入部に続く二度目の米沢の春でした。その担当者には近習(側に仕える役目)の佐 藤文四郎を任命し、田は米沢城の西南、遠山村の四反余(約40アール)を選び、準備が進められました。
3月26日の朝、鷹山は家臣を連れ白子・春日両神社にお参りしたのち、初めに鷹山公が自ら3鍬を入れ、続いて奉行3人が9鍬ずつ、以下佐藤文四郎・郡奉行などが45鍬、代官などが72鍬、下役が99鍬、遠山村の肝煎(きもいり=村役人)と農民が300鍬を入れ、全員で神社からの神酒をいただいて終了しました。
また、当時の農民は学習する機会がなかったので鷹山は常識を学ぶ機会を設けました。
目先のことばかりだけでなく長期的な視点を持てるように、集団における常識と義務、また人生観を示そうと農民への教育を強化していったのです。
苦難を乗り越えた先の一体感
鷹山による再建は右肩上がりになりつつありましたが、ある年に江戸の2つの邸が火災で消失するという災難が起こりました。
ようやく立て直してきたときに・・・と頭を悩ませた鷹山でしたが、この頃には鷹山の周りには理解者が増えていて、家臣の中でも自発的に動いてくれる人が現れていました。
かつて争いのあった五十騎組がリーダーとなり、新築のための伐採や運搬を。武士階級は当時労働なんてもってのほかという時代だったのにも関わらず、率先して労働奉仕を申し出たり、藩のためにと全力を尽くしてくれたのです。
安堵の後に起こった七重臣の反逆
一方で、重臣の中であからさまに命令に反抗するものも現れました。
改革は進みつつある。そう思っていた矢先、事件が起きた。突如、米沢城の鷹山の元へ家臣たちが駆け込む。突き出されたのは、改革を完全に否定する訴状だった。「一汁一菜や木綿の衣服などというのは小事に過ぎない」「武士に農業をさせるとは、鹿を馬とするような馬鹿げた行いだー」。訴状に署名したのは、代々上杉家に仕えてきた名家の7人。性急すぎる改革が保守派の激しい反発を招いていたのだ。改革の中止を認めるまで、部屋から出せないと凄む重臣たち。
4時間以上も続いた押し問答の末、騒ぎを聞きつけた家来が助けに入り、鷹山はなんとか脱出した。
THE歴史列伝
鷹山が下した処分は、7人のうち5人を隠居・閉門、2人は切腹。裏で手を引いていた儒学者・藁科立沢(わらしな・りゅうたく)は斬首という、厳しいものだった。23歳の鷹山は、改革を進めるため断固たる意志で抵抗勢力を一掃した。
七人は前日、嘘の通知を城内にながし、当日は誰も鷹山の警護をするものはいませんでした。
唯一、近習の一人が出仕停止命令に漏れていたためこの騒ぎを聞きつけ、事件は未遂に終わりました。
養父重定は全員の切腹を勧めましたが、鷹山は「自分に至らないところがあったのではないか」と改め、城内の御堂へ籠もり祈願をし、改めて是非の判断に誤りがないようにと反省をしました。
七人が出した訴状の判断を公正にするべく、七人以外の幹部や配頭、三十人頭も呼び出しましたが誰も訴状の内容に賛成しませんでした。
そこでようやく、鷹山は七人の処分を決定したのです。
実はこの事件には黒幕がいて、鷹山が教えを仰いでいる細井平洲への嫉妬と妬みから、米沢藩の儒医だった藁科立沢が手を引いていたという事実が発覚し藩内は騒然となりました。

鷹山は、幾度となく訪れる災難を突破してきましたが1775年の正月、数え年25歳になったときに「厄払いの全廃」の決断をしています。
それは、寿命の長短は天命であり、ある年に限り吉凶などということはありえない。仮にあったとしても、それは自分の行いによって運命が定まるものである。と言う言葉を残しているのだそうです。
旧行事の撤廃となると、習慣づいているものから反発が起こる。
それをわかった上で、自分が厄年の時に全廃することで信頼を得ようとしたのではないかと思うのです。
これも大倹令と同様、藩全体の相当な出費を改めようとしたからだとされています。
次々と状況を打破していくの決断力
鷹山は、藩の再建にともない自発的に協力していくようにと取箇帳を一般家臣に公開しました。
それを受けて、竹俣当綱は領内の産物の生産性を上げる事をたてました。
まず、樹芸役場をもうけて漆方、桑方、楮方の三つに分けてそれぞれに担当を置き、百本ずつ苗木を植えさせることにしたのです。
その苗木で出来た農作物は、一定の価格で買い上げるとし、農民の生産意欲を大きく向上させました。
それについで、米沢で取れていた青苧をただ販売するだけでなく、それを加工して織物にするために奔走し、ようやく縮師・源右衛門一家と織工五人を雇い米沢に連れ帰りました。
天明の大飢饉を凌ぐ
江戸時代は飢饉がよく起きましたが、天明の大飢饉と言われたものは歴史的にも大きな災害でした。
鷹山の功績として名高いのが天明の大飢饉(1782年)における米沢藩の処置です。藩士、領民の区別なく一日あたり米3合の粥を支給し、酒、酢など、穀物を原料とする品の製造を禁止するとともに、被害の少なかった地域から米を買い入れるなど迅速な対応が功を奏し、仙台藩では30万人が餓死したといわれる大飢饉の中で、米沢藩では一人の死者も出さず、江戸幕府から表彰されています。
上杉鷹山と米沢平野の開発
米沢藩は元々田地が痩せ、山地が多いために米の収穫量も不安定。
鷹山はそれを見越し、備籾倉という米の備蓄が出来る倉を、天明の飢饉が起きる九年前に建てていました。
さらに、家臣たちも、また民間でも郷蔵を建てさせて、備蓄が出来るごとに報奨金を与えるなど積極的にすすめていきました。
1782年、9月頃に鷹山は警戒を命じ、合わせて酒や糀、菓子や豆腐や納豆など米や豆を加工するものは停止としました。
稲のなりが悪く、天候の不調は回復せず、日に日に凶作が確実になり、とうとう収穫の時期を迎えてもほとんど米は採れませんでした。

そこで、備籾倉を開放し、救援米が藩内に送り出されました。
また、この米を粥にするようにと自らも三度の食事を粥として民衆と同じ食事を取ったといわれ、その姿に上杉家全員が習い、米沢藩では死者は出なかったということです。
隠居してもなお衰えない、鷹山の手腕
この飢饉を脱した頃、鷹山は藩主の地位を養父重定の次男である治広に譲りました。
このときに治広に送った心得である「伝国の辞」は、今でも広く知られています。
伝国の辞でんこくのじ
伝国の辞/なせば成る~
一、国家は先祖より子孫へ伝え候国家にして我私すべき物にはこれ無く候
(国(藩)は先祖から子孫へ伝えられるものであり、我(藩主)の私物ではない)
一、人民は国家に属したる人民にして我私すべき物にはこれ無く候
(領民は国(藩)に属しているものであり、我(藩主)の私物ではない)
一、国家人民の為に立たる君にて君の為に立たる国家人民にはこれ無く候
(国(藩)・国民(領民)のために存在・行動するのが君主(藩主)であり、”君主のために存在・行動する国・国民”ではない)
右三条御遺念有間敷候事(三ヶ条を心に留め忘れなきように)
天明五巳年二月七日 治憲 花押
治広が初めて国入りをし、城内で財政についての大評定が開かれました。
これに鷹山も参加し、予算を半減して借り入れをせず歳入のみで歳出を賄うこと。としました。
この頃には鷹山と共に手腕を発揮した莅戸善政や竹俣当綱はおらず、次期担当は政策をただ実直に遂行し続けていたため次第に収益が減り負債がかさみ、再び藩内の財政は傾いていたのです。
鷹山の後見を、という声が家臣や領民の間に流れ始め、鷹山は治広をたてながら再び総務を総括することになりました。
藩再建の要になった16年計画
歳入を十五万石の半分の七万五千石として、新たに予算編成が組まれました。
それまで厳しく取り立てていた年貢は、滞納分は長期分割として、疲弊している農民たちへは命令を緩和した。
さらに、養蚕を盛んにするために桑の苗を農民に与え、桑が成長してから桑畑などの開墾費用を回収することとしました。
鷹山自身も養蚕を行い、家臣もまたそれに習いました。
絹織物を始め、麻織物の技術の向上もありどんどん米沢織は広まっていきました。
これは今でも米沢織として、最高級品と言われています。
また、馬の開発も積極的に行い国産馬の改良を重ね、どんどん藩の収益は上昇していきました。
鷹山の深い情愛
鷹山は、当時高齢化が進み藩内では労力にならないと疎まれていた老人を敬うべき、という教えを広めようと「敬老会」を開催し、この日は孫や子が付添い給仕し、自然に老人を大切にするような気風を育てていきました。
また、十五歳以下の子供の子を五人以上育てている者には未子が五歳になるまで扶持を与えるなどの策を講じました。
さらに、鷹山はこれまでの五人組という自治組織を改めあらたに町在伍什組合を設置しました。
そこで新たにあらためて伍什組合ならびに近隣の五ヵ村組合を設けることとする。
移ろうままに
五人組は、常に睦じく交わって苦楽を共にすること家族のようでなければならない。
十人組は、時あれば親しく出入してお互い事情を理解しうこと親類のようでなければならない。
ひとつの村では互いに助け互に救い合ってその頼もしさは友人のようでなければならない。
五ヵ村組合の村同士は苦難にあって相互に助け合い、隣村同士のよしみの甲斐あるようでなければならない。
このようにそれぞれ組ごと絆を強くして交流し、老いて子がなく、幼くして親がない、あるいは貧しくて養子得難く連れ合いに先立たれ、あるいは身体の不自由ゆえ身過ぎままならず、あるいは病気治療行き届かず、死んでも弔いなしがたき、または火事にあっては雨露しのぎがたき、変災に遭っては一家立ち行き難き、かように難儀いかようにもし難きものがあるならば、まずは五人組がわが事として世話致し、それで及ばぬ事あれば十人組が力を合わせ、それで及ばねば村での世話で難儀を除き、その生涯それ相応無事のうちに遂げしむるようにしなければならない。さらにそれ、もしも一村大なる災害に襲われその村立ち行き難きほどの危機に際しては、近隣の村はよそ事として傍観することなく、かかる時ほど近隣のよしみ、四ヵ村頼もしく救済にあたらなくてはならない。
町に住む商人と農村に住む村民の双方が互いに助け合って行くようにという組合のこと。
これにより反体制の温床を防ぐとともに、米沢藩では百姓一揆などのクーデターが起こらなくなっていったそうです。
惜しまれこの世を去った鷹山の名言
苦難を乗り越え、基礎を固めていき、治広も四八歳になり、隠居。
十二代目を斉定が継ぐと、鷹山は治広とともに時折ご意見番として相談にのるも政権から離れ、やがて七十歳の生涯を閉じました。

鷹山が家督を継いだときには毎年の不足金が三万両。
借入金の元金は十一万両あまりあったものが、鷹山が没した翌年頃にはほとんど零。
さらに軍資金として五千両と備蓄を持つほどに藩の財政は好転していたのだから、その政治手腕、どん底からの底力と粘り強さ。
そしてどんなときでも、人に対して尊敬と愛を持ち続けた鷹山。
ケネディ大統領が日本記者から「あなたが日本で最も尊敬する政治家は誰ですか」と聞かれたとき「それは上杉鷹山です」と答えたそうです。
鷹山の残した「なせば成るなさねば成らぬ 何事も 成らぬは人の なさぬなりけり」という名言が生まれた背景には、これまでの鷹山が抱えたたくさんの重みを感じますね。
>>上杉鷹山に興味が湧いたら最初に読んでほしい本
 | 【中古】 名指導者上杉鷹山に学ぶ / 鈴村 進 / 三笠書房 [単行本]【メール便送料無料】【あす楽対応】 価格:330円 |
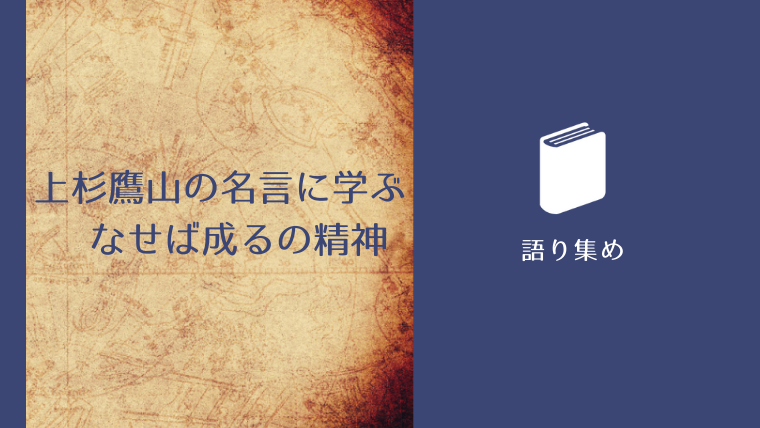
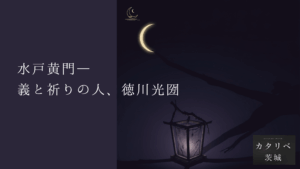
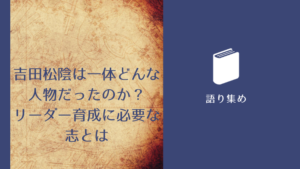
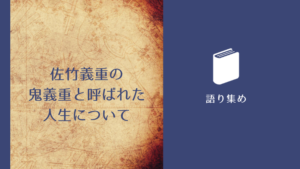

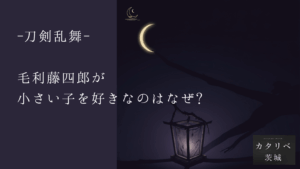
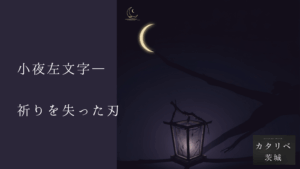
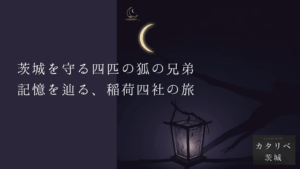

コメント