ひとりの少年の姿をした刃が、こちらを見つめている。
その瞳は深い夜のように冷たく、まだ幼い声で問いかける。
「あなたは・・・誰かに復讐を望むのか?」
小夜左文字。
その小さな刀身には、一人の母と子の悲しみが刻まれている。
左文字の血脈に生まれし短刀
鎌倉時代の越前国、今の福岡県の名刀左文字により作成された短刀。
表は中央に「佐」、裏は「筑州住」。
左文字一派と言われるようになったきっかけとしてこんな話がある。
「左文字」という呼称には、由来とされている伝説があります。
引用元:刀剣ワールド
相模国で日本刀の名匠正宗から相州伝の技巧を学んだ「安吉」(やすよし:後の左安吉・左文字)は、人格が優れ巧みな腕前を持っていたことから、師である正宗と門徒たちに大変親しまれました。師事期間を終え、安吉が故郷である筑前国へ帰国する際には、別れを惜しんだ師弟たちが見送りの予定場所を越えて彼に付き添いました。その際、師である正宗は自身の「片身」だとして己の左袖をちぎり、安吉に渡しました。これに感極まった安吉は、正宗より授かった左袖を家宝とし、左を姓とした「左安吉」を名乗り、作品の銘にも左の字を切るようになりました。
そして、左安吉は左文字とも呼ばれるようになり、ひいては一門の名も左文字となったのです。
恩に報い、想いを受け継ぐためにつけられた「左」の一字。
その系譜は、短刀の名匠として幾世代にも続いた。
初代安吉を筆頭に名刀を生み出しているが、主に短刀が多い。
太刀は江雪左文字のみである。
小夜左文字(さよさもじ)
引用元:刀剣鋼月堂
指定:重要文化財
銘:左(名物 小夜左文字)
筑州住
所蔵:法人蔵
種別:短刀
流派:左文字派
刀剣乱舞の作中でも、短剣としてのステータスは他の刀に比べても能力は高い。
生存・打撃・統率はトップ、必殺は太鼓鐘貞宗や不動行光と同率で初期に活躍してくれる短剣である。
小夜左文字のキャラは刀剣男士の中でも子供の姿を取っている。
服装は法衣を模しているが、これはその名のもととなった西行法師と関連しているのではないかと思われる。
「年たけて またこゆべしと 思ひきや 命なりけり 小夜の中山」
という西行法師の和歌にちなみ、所有者であった細川幽斎が「小夜左文字」の名を付けた。
この和歌は、関東超えの難所とされていた三重の鈴鹿・静岡の中山・神奈川の箱根の旅について読んだ歌である。
こうして難所を越えていけるのも、生命があって生きてこられたからだという喜びを表現したものであるが、これについて作中ではこう呟いている。
「僕は小夜左文字。西行法師の歌から名付けられたんだ。
・・・でも、僕が見い出された原因はそんな綺麗なものじゃない。
血と怨念にまみれた、復讐劇だよ・・・」
度々回想シーンでも、この言葉は登場する。
この小夜左文字が生まれるきっかけとなった伝説が、静岡の中山に伝わっている。
夜泣き石に宿る声
その昔、小夜の中山に住むお石は、夫の帰りが遅かったため、菊川の里に仕事を探しに出掛け、その帰宅の途中、小夜の中山の丸石の所でお腹が痛くなり、松の根元で苦しんでいる所へ轟業右衛門(とどろきごうえもん)が通りかかり、彼女を介抱したとき、懐に金の袋を見つけ、お石を殺して金を奪った。
そのとき、お石は懐妊していたので、傷口より子供が生まれ、お石の魂がそばにあった丸石にのりうつり、夜毎に泣いた。これを夜泣き石という。傷口から生まれた子供は音八と名付けられ、九延寺の和尚に飴で育てられ、大和の国の刀研師の弟子となった。
引用元:滝沢馬琴の伝説「石言遺響」
そこへ轟業右衛門が刀研にきたおり、刃こぼれがあるので聞いたところ、「去る十数年前、小夜の中山の丸石の付近で妊婦を切り捨てたときに石にあたったのだ」と言ったので、母の仇とわかり、名のりをしてめでたく仇打ちをした。その後、弘法大師が九延寺の観世音を点眼し、夜泣き石の伝説を聞き、お石の菩堤の為に丸石に仏名を書いて立ち去ったという。
いくつか似たような話がこの中山峠には存在するが、いずれも後家の妻が命と共に短刀を奪われ、生存した子が復讐を成し遂げるといった物語。
実際に静岡県掛川市の公式HPにはこの夜泣石についての記述がある。
この仇討の際に言ったとされるのが
「今宵の立会……盲亀の浮木、優曇華の花待ちたること久し、此処で逢うたが百年目!親の仇だ!いざ、尋常に、勝負、勝負!」
という言葉であるが、これがスマホ版公式ゲームのログイン時につぶやくセリフの元になっている。
裏切られ、刃は彷徨う
回想シーンでは小夜左文字の「復讐」というエピソードが多く話されているが、例えば畑の内番では「飢饉は避けたいよね…」という台詞があるがこれにも逸話がある。
佐文字の刀は、復讐を遂げたあと人の手を渡り歩く。
一時は遠江国掛川藩の山内一豊の手中に移るが、その話を聞いた細川幽斎に懇願され、譲渡したとされている。
その後は細川幽斎が存命中に子の細川忠興が受け継いだ。
しかし、この三男である細川忠利の代に小倉藩大飢饉が起こった。
その折、忠利は領民の飢餓を救うために、この名刀と主君より拝領した品である「有明の茶入」という茶器とを合わせてまとめて売りに出したという話が残されている。
ゲーム中でも、万屋へ行くと「僕を連れて行くなんて、お金に困ったの?」というコメントが表示される。
売られ、手放され、信じるたび傷つく。
その記憶は、今も刀の心に沈殿している。
常に裏切りと共にあった左文字の刀の性質を受け継ぎ、人を疑ってしまう性格であり、特に初期の頃は主をあまり信用していない。
不幸三兄弟
左文字はゲーム中では3兄弟の末っ子として登場する。
長兄の江雪左文字、次男の宗三左文字。
兄たちからは「お小夜」という名で呼ばれている。
彼らは別名不幸三兄弟と呼ばれたりもするが、それぞれに背負った運命はどれも平坦ではない。
小夜左文字の身なりは法衣であるにもかかわらず、どこか荒々しい服装であるのは、小夜左文字がかつて山賊の刀であった事にもよるのだろう。
左文字が身につけている赤い紐の笠は女性物ではないか?という説があり、無念にも殺されてしまった母親の形見ではないのか。と言われている。
夜が明ける日は来るか
小夜左文字は度々心の内を呟いているが、いずれも復讐が果たされたのに満たされない虚しさ、悲しさ、寂しさが伺える。
ゲーム中では、江戸が舞台の「延享の記憶」を燭台切光忠と同行すると多くの回想シーンが再生されるそうだ。
「刃は冴えても心は冴えず」
「胸の奥に焼付いた、この黒い澱みは……いつになったら……っ」
「もはや復讐が果たされているのに……僕はっ……復讐を求めてしまう…!」
夜泣き石はいまも中山に残り、母の涙が伝えた祈りは、風に震えている。
復讐を遂げたその先にも、小夜の心には闇が残った。
だが、歴史の中で断たれた祈りを拾い上げ、刃を抱える審神者がそばにいるなら・・・
彼の夜にも、いつか朝が訪れるだろうか。
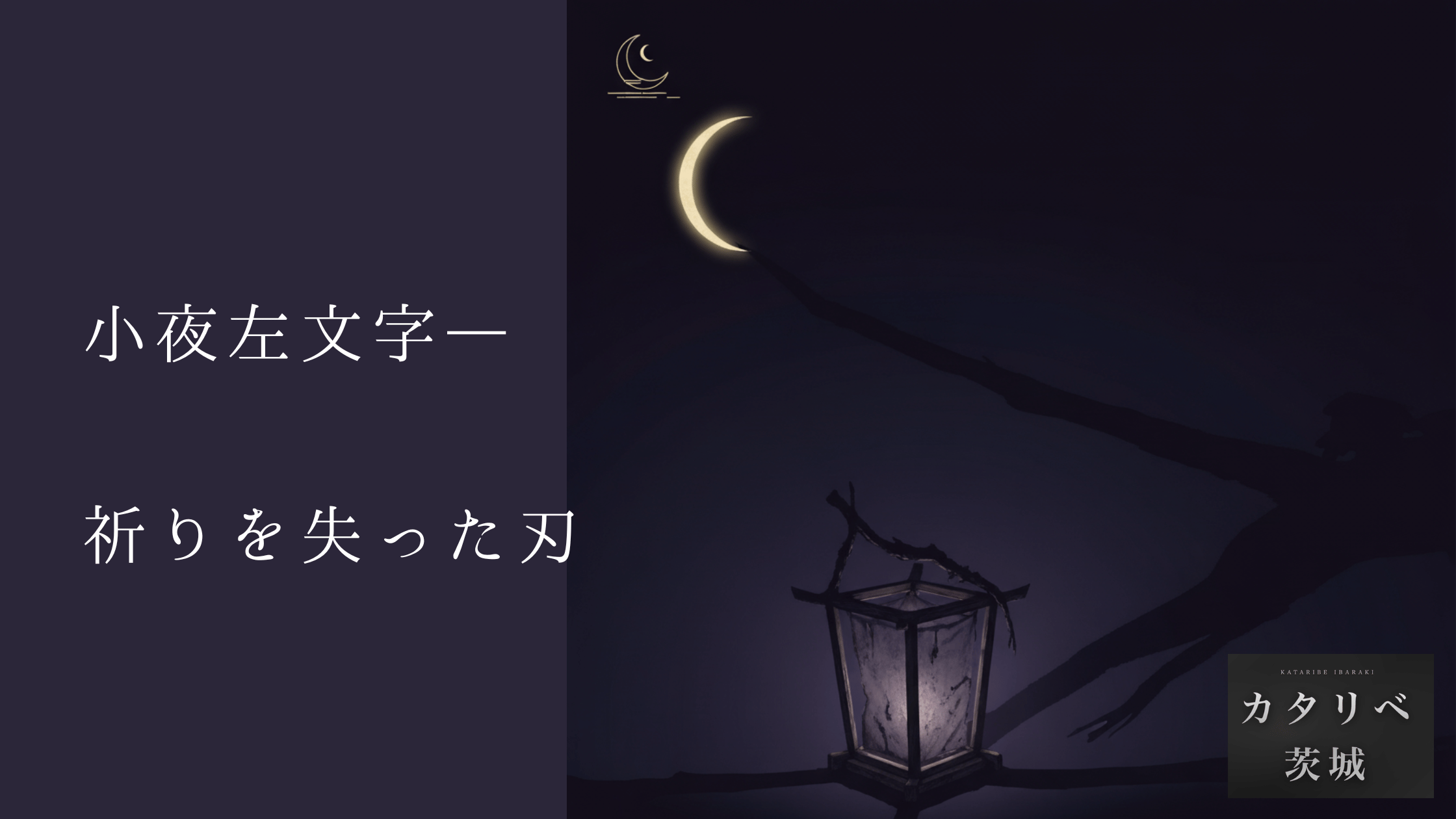
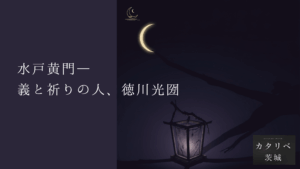
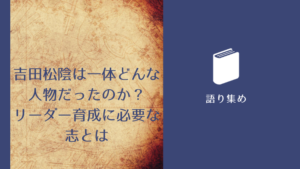
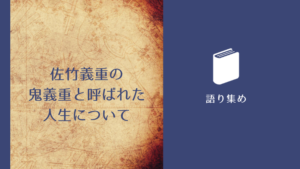

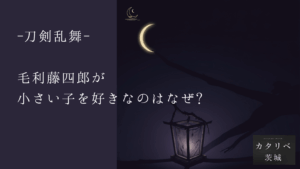

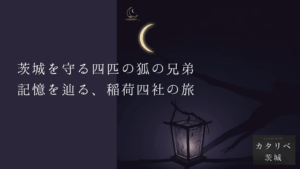

コメント