わくわくした瞳で彼はそれを見据えていた。
「おぉ……!小さい子ですかね?これ」
うっとり愛おしそうに微笑む彼自身のみてくれは、その「かわいい」と呼ぶ対象と同じ年なのではないか?と思えるほど幼く見える。
彼がそこまで小さい子を愛でるのに、一体どんな歴史があったのだろうか。
粟田口吉光の短刀 ― 毛利藤四郎
毛利藤四郎(もうりとうしろう)は、粟田口吉光作の短刀である。
銘は「吉光」。鎺(はばき)は金無垢で、「吉光うめたた寿斎」と在銘されている。
粟田口吉光は生まれについて諸説あるが、出身は越前の領民だろうとされる。
本来は吉光の名で呼ばれるが、通称の藤四郎で呼ばれることが多く、その殆どに「藤四郎」の名前がつく。
そのため、ゲーム中でも藤四郎四兄弟といいながら、同じ刀工から生まれたとしてたくさんの刀剣男士たちが並ぶ。
例えば、鯰尾、骨喰、薬研、厚、乱、博多、後藤、信濃などが名前に藤四郎が付き、作中では一期一振が長男とされており、刀剣乱舞のゲーム中では「いち兄」と呼ぶ姿が見られる。
鍛冶のみならず書は弘誓院流を学んだとされ、銘字も優雅な書体となっている。
短刀 銘 吉光(名物 毛利藤四郎)
引用元:名刀幻想辞典
8寸8分5厘(刃長26.5cm)、内反り
東京国立博物館所蔵
「ツチノコ」と呼ばれた刀
2017年頃までは、毛利藤四郎は大阪城イベント「地下に眠る千両箱」で実装された刀剣男士としてイベント発生時のボスドロップのみで入手可能となっていた。
更に、ドロップ率の低さから入手が極めて難しく稀であった。
そのため、審神者からは「藤四郎兄弟のツチノコ」と呼ばれていたほどだ。
しかし、2018年のメンテナンス以降、鍛刀でも入手可能となり、その姿を目にする機会は増えた。
藤四郎兄弟たちは画像を見ると警備隊のような装いをしているが、毛利藤四郎も例外ではない。
故に、内番時の彼のジャージはコスチュームとしても人気が高い。
小さい子が好きな毛利藤四郎
毛利藤四郎といえば、「小さい子が好き」という性格描写が有名だ。
「うわぁー、小さい子、可愛いですよね。いや、僕の身長はさておき」
「小さい子の、お守りですか?」
「おぉ……!小さい子ですかね?これ」
その言葉の端々に、彼の優しさと庇護欲がにじむ。
この“子ども好き”の根にあるものを探ると、史実の背景が見えてくる。
毛利輝元と周姫 ― 美しき悲劇の記憶
とうらぶ公式のTwitterで毛利藤四郎はこうツイート表示されている。
粟田口吉光作の短刀。藤四郎兄弟のひとり。
毛利家にあったことが名の由来。
小柄なことを利用した変則的な戦い方を得意とする。
話を聞くことと、(自身の身長はさておき)小さい子が好き。
毛利藤四郎は、毛利輝元に所持されたことからその名がついた。
輝元が11歳で家督を継いだとき、この短刀も譲り受けたとされる。
彼の周囲には、悲劇的な逸話が残る。
毛利輝元が、児玉元良の屋敷の前を通りかかった時に見かけた娘(周姫)が大変美しく気に入り、度々この家を尋ねるようになった。
これを快く思わなかった元良は娘が12歳になると同時に、毛利家に仕える杉元宣に嫁がせたが輝元は諦めきれず、元宣を暗殺。
元宣は菩提寺である興元寺に奉られ、毛利の家臣だった杉家は断絶。
側室となった周姫は密かに二の丸様と呼ばれた。
長らく本室との間に子供がいなかった輝元は、この周姫との間に3人の子供を授かった。
しかし、周姫は美人薄命の定めか、心身ともに疲労があったか、32歳の若さでこの世を去った。
子供は、本家萩初代藩主、徳山藩主、岩国吉川家に嫁ぐなど、周姫は正室が許さなかったために毛利家の墓にも入ることなく、山に葬られたとされている(後の善生寺)。
これを憂いて、藩主となった長男次男は、それぞれ寺の建立や読経を絶やさなかかったりと母の生涯を偲んだという。
明治になり、香山公園(瑠璃光寺)にある毛利家菩提所の裏に墓が移された。
一方、暗殺され興元寺で祀られている杉元宣についても噂があり、周姫恋しと夜な夜な白馬に乗って出かける為この寺の正門は閉められたままにされ、半世紀前までは開かずの門になっていたという。
周姫も遺言を残しており「もう輝元公は正室様にお返しをして、私はあの世に参り、先の夫・杉元宣公の傍に行きおわびがしたいが、はたして元宣殿はこの私を許してくださるでしょうか」と病の枕辺で侍女たちに語ったという。
これらの逸話には、美しさと哀しみ、そして「幼くして運命に翻弄された者たち」の影が重なる。
毛利藤四郎が“小さい子”や“守るべき存在”に強く心を寄せるのは、
そんな主の記憶を映しているのかもしれない。
姫山のお万伝説 ― 美しさが呼んだ祟り
山口にはもう一つの伝承がある。
美しい娘・お万が殿に見初められ、拒んだ末に父を殺され、井戸に蛇攻めにされた・・・
という凄惨な物語だ。
これも検索すると様々出てくるが、山口の伝説として残されているのがこちら。
むかし、山口の城下に住む長者のところに、お万というひとり娘がいた。お万は、色白で、目のぱっちりした、笑うと小さいえくぼのできる美しい娘であった。十七、八になると、その美しさは歌にまでうたわれるほどの評判になった。ある日、しばいの見物に出かけたお万は、わかい旅役者をひと目見て好きになった。そんな時、城下をまわっていた殿さまが、美しいお万に目をとめた。「そちらの娘をよこせ。そうすれば、そちの願いをなんでみかなえてつかすぞ。」と命じた。お万には、すでに好きな相手があるので、長者は返事をためらっていた。すると、気の短い殿さまは、すぐに承知しない長者に腹を立て、「なぜ返事をせぬ。余の申すことが気に入らんとでもいうのか。」「いえ、めっそうもございません。しかし、娘の気もちも聞いてみませぬと・・・。」「そうか。では、お万によく言い聞かせて、きっと余の意にそうようにせよ。」殿さまの言いつけにそむけば、どんなおそろしいめにあうかよく知っていた長者は、家に帰ると、すべてをお万にうちあけた。お万は、「お父様の言いつけなら、どんなことでもしたがうつもろです。でも、そればかりは・・・。」と、泣いて長者にすがった。長者は、「よくわかった。無理もないことだ。どのようなことがあろうとも、このことはお断り申してこよう。すぐに城に出かけた長者は、いつまでたっても帰ってこなかった。お万をはじめ、家のものが心配していると、突然どやどやと殿さまの家来が屋敷の中に入ってきた。そして、いやがるお万をむりやりつれて引き上げていった。城へつれてこられたお万の前に、あらなわでしばられた長者が引きすえられ、胸もとへ刀をつきつけられた。殿さまは、「お万、そちはどうしても余のことばにさからう気か。あれを見よ。そちの返事しだいでは、父親の命はないものと思え。」と大声でいった。お万は、なみだにぬれた顔をあげて、「お殿さま。どうか、このことばかりはお許しください。それ以外のことなら、どんなことでもいたします。どうか・・・。」と、ひたすら、殿さまににお願いするばかりであった。「だまれ。ふとどきもの。どうしても余の言いつけにそむく気だなっ。」いかりくるった殿さまは、お万をしばりあげ、「ものども、ただちに父親の首をうて。このお万は姫山に送り、いただきの古井戸の中にいれてヘビ攻めにせよ。」と命じた。長者は、その日のうちに首をはねられた。姫山の古井戸に入れられたお万は、毎日投げ込まれる多くのヘビに攻め立てられた。お万は、その苦しみと父親を失った悲しみとで、日ごとにやせ細って、なげき苦しみながら死んでいったという。それからというもの、お万のうらみがこの山に残ったのか、姫山の見える山口の地からは、決して美しい娘は生まれなくなったと伝えられいる。
引用元:山口の伝説
この“美貌ゆえの悲劇”もまた、周姫と重ねられる民話のひとつとされる。
戦乱の中の短刀
毛利藤四郎という刀剣は、毛利輝元や周姫といった幼くして城へ身を寄せた子供を守ろうとする思いが強いのかも知れない。
ログイン時のこのセリフや、結成時、万屋での言葉にも、
「小さい子、いますかねぇ」
「小さい子の引率ですか?」
「小さい子のおやつでも買うんですか?」
などと、自ら子守をかって出ようとする姿が垣間見える。
毛利輝元は父の急逝後、11歳という若さで家督を継いでおり、この時に毛利藤四郎も譲り受けたとされる。
輝元の死後、この刀は徳川家康に献上され、関ヶ原の戦いの頃に家康により池田輝政の手に渡ったと言われている。
それから長らく江戸期には池田氏のもとにあり、その後は明治天皇に献上されたという。
戦乱を越え、主を変えながらも、彼は静かに“守る”という役割を果たし続けた。
ゲームにおける毛利藤四郎
刀剣乱舞では、彼の小柄さが戦闘スタイルにも反映されている。
「子供殺法、股下ぐるり!」
このユーモラスな台詞に、彼の軽やかさと芯の強さが表れている。
ちなみに、刀帳まとめ情報によると毛利藤四郎の身長は132センチとされている。
それ以下の刀剣男士は「かわいい」認定され、「うちの子」と呼び可愛がっている。
例えば、蛍丸、小夜左文字、謙信景光、包丁藤四郎、平野藤四郎、秋田藤四郎、愛染国俊。
彼らを畑当番や馬当番、手合わせ練習などの内番で相手にすると
「小さい子とお馬! 可愛い!」
「小さい子とお馬! 可愛さ極まれり!」
「ふぎゃー!うちの子ながら可愛さ極まれり!」
などという特殊台詞を発する。
この愛情の深さは、単なるキャラクター性を超え、“守ること”を運命づけられた刃の記憶そのものだ。
作品中の声と姿
毛利藤四郎のイラストは、猫缶まっしぐら氏、声優は高城元気。
修行に旅立つ仲間を見送る際には、こんな言葉を残す。
「成長のための旅ですか、小さいままのほうがいいと思うんですけど」
その台詞には、彼自身の祈りが宿っている。
どうか、これ以上傷つかないで。
どうか、今のまま笑っていて。
余談
関ヶ原の戦いでは、毛利輝元は石田三成などの説得を受け、西軍の総大将として大阪城西ノ丸にはいったものの本陣には出陣せず、大阪城に籠もった。
兵力を持ち、難攻不落と言われる大阪城にいたにも関わらず出陣せず、引き上げたことで「輝元は無能だ」と広がる原因となった。
戦国の世において、戦わずして逃げることは意気地がないということなのだろう。
その時、刀剣は輝元の手を離れて東軍の池田家のもとにあった。
ゲーム中、関ヶ原ステージではソハヤノツルキと一緒に出陣すると、当時のお互いがそれぞれの大将のもとにいたことが伺える会話を聞くことができる。
「向こうにつきたかったという思いでもあるのかい?」と聞くソハヤノツルキに対し
「どうでしょう。輝元様は結局出陣しませんでしたから。僕がいても変わらないですよ」
と答えている。
結び ― 小さき刃に宿るもの
毛利藤四郎は、ただの短刀ではない。
戦乱の世に生まれ、主の哀しみとともに語り継がれた“記憶”である。
「時を越え、かつての主のその後を見届けてきた毛利藤四郎です。僕は、主さまを置いてどこかに去ったりしませんから」
その一言の裏にあるのは、誰かを守りたかった少年の面影なのかもしれない。

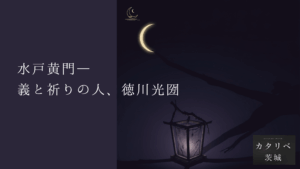
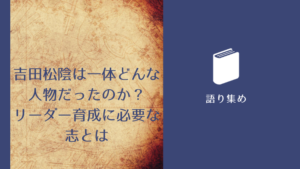
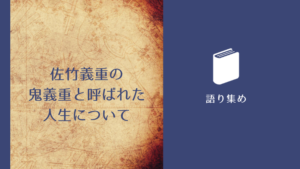

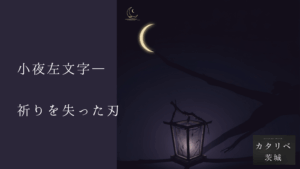

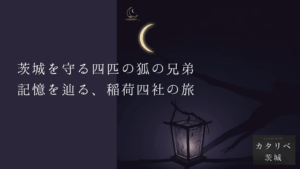

コメント